京都大学農学部の6つの学科ってぶっちゃけどう違う?
「京大農学部を受けよう!」と決めたのはいいものの、学科選びってどうすればいいの?
京大農学部を志望する人なら、少なくとも一度はこの悩みにぶつかるのではないでしょうか。
実際、私もそうでした。「何となく農業や環境問題を扱っている感じがするけれど、そもそも農学部って何をするところなんだ?」というところから始まり、学科によって何がどう違うかもよく分からない。
パンフレットを見ても専門用語ばかりでピンとこなくて、結局、「なんとなく興味がある分野っぽいから」「人気がありそうだから」みたいな理由で決めてしまう人も多いです。(実際、京大に入ってみると、学科の名前と何となくのイメージで決めた人はかなり多かったです。)
でも、ちょっと待ってください。
実は、京大農学部は、学科ごとに忙しさや授業の自由度、学ぶ内容の深さがまったく違います。
学科によってはほぼフルコマで実験に追われる生活になるところもあれば、比較的自由に授業を選べてバイトやサークルと両立しやすいところもある。学科の雰囲気も大きく異なり、いわゆる「研究ガチ勢」が多い学科もあれば、のんびりした空気の学科もあります。
受験期の私は、こうしたリアルな違いが全く分からず、とにかく手探り状態でした。幸い(?)浪人中に時間があったので、暇な時間に授業のカリキュラムを調べたり、先輩の対談記事を漁ったりして何とか比較はしたけれど、はっきり言って、現役の受験生がそこまで時間を割くのは難しいと思います。
だからこそ、この記事では「パンフレットには載っていない学科ごとのリアルな違い」を、実際に学んだ経験をもとにお伝えしたいと思います。受験から6年も経っている上に、完全に主観が入った内容にはなりますが、少しでも、納得のいく学科選びの助けになれば嬉しいです。
学科選びのポイント
京大農学部は、出願時に第1希望から第6希望まで出す必要があります。そして入試の点数順に学部の合格者(たしか300人?)が決まり、上から希望の学科へ振り分けられるシステム。人気の学科は点数上位の人たちで埋まるので、「人気だから」「偏差値が高いから」と選んでも、結局希望通りいかないこともあります。
ここで注意していただきたいのが、
あなたは本当に、「人気だから」「偏差値が高いから」という理由で良いのか?
という点です。
大事なのは、4年間をどう過ごすか。
正直、人気のある学科は、学業や研究で多忙な生活になりがちです。(応用生命、食品など)
受験の時に偏差値や何となくのステータスを基準にして興味の無い学科に通ってしまうと、かなりしんどい4年間を送ることになります。(一応転学科の制度もありますが、これはイレギュラーなケースなので、今回はいったん考えないことにしますね。)
本当にやりたい・興味があるのならもちろん第一希望に書くべきですが、偏差値や人気度で選ぶのは、私はあまりオススメしません。(実際、受験の時に人気のある学科だからと全く興味の無い学科に入ってしまい、周りの人との熱量の差に悩む人を何人も見てきました…。)
学科によって授業の自由度や忙しさ、友達との距離感も全然違うので、可能であればその辺りをしっかり考えて選ぶのがポイントです!
各学科のリアルな雰囲気
ではここからは、各学科のリアルな雰囲気を私の主観全開でお伝えします。
1. 応用生命科学科(たぶん人気No.1!)
バイオテクノロジーや高分子化学など、生命科学を比較的ミクロな視点から研究する学科です。発酵や醸造など、食品系の研究室も少しあります。
学科の人数は50人程度で、ほとんどが必修授業のはず。ほぼ常に学科のメンバーで授業を受けるので、独りぼっちになったりすることは少なそうです。
実験系の内容が多く、特に3年生になると、ほぼ毎日、専門科目の授業と実験で埋まります。真面目で研究熱心な子が多い印象で、本当にこの分野が好きな人にとっては最高の環境だと思います。(忙しいはずなのにとても楽しそう。)逆に、授業はほぼ必修で選択の余地もあまり無いため、興味がないと結構キツイと思います。受験時に「人気の学科だから」と選んでしまうと後悔する可能性があります。
ちなみに、ミクロなことをやっている研究室が多い印象ですが、私の友達は農場で野菜を育てていました。ある程度の内容の幅はあるのかもしれません。
2. 地域環境工学科(工学系に強い)
農学部の中でも珍しく、工学寄りの内容が多い学科です。水環境やエネルギー開発、フィールドロボティクス、生物センシングなどを学ぶことができます。生物系がメインの農学部ですが、この学科では数学や物理を使うことが多いので、理系科目が得意な人向けかもしれません。
だからなのか、少しサバサバして落ち着いた雰囲気の子が多い印象です。みんな真面目で賢そう。(あくまでも外から見た印象です。)40人弱と比較的少人数で、特に女子は少なめなのかな。集まって談笑する姿をよく見ます。大人しそうだけど、芯やこだわりがあって優秀なんだろうな…、と、勝手に思いながら見ています。仲良くなったらかなり面白いのではないかと思っています。が、私自身この学科にほとんど友達がいません。一番未知の学科です。残念。
3. 食料・環境経済学科(農学部の文系枠)
「経済」と名の付く通り、農学部の中では文系寄りの内容を学ぶことができる学科です。食糧問題や環境問題、農業経済や経営、貧困問題、人口問題、貿易問題、自然保全など、かなりマクロな問題を扱っています。”そもそも農学とは何か” といった大きなテーマを考えたり、都市と農村の歴史を紐解いたり、政策の視点から木材の流通を見たり。かなり社会学的な内容も多い印象です。
私もよく授業を受けていましたが、おそらく実験はほぼなく授業の自由度は高め。バイトやサークル、就活に力を入れる人も多そうです。逆に言うと、実験などの技術的な専門スキルは身に付きにくいので文系就職する人が多い、と食環の友達はボヤいていました。
ちなみに私はこの学科が開講する海外研修に参加し、フランスでワインビジネスを学んだことがあります。いやぁ、楽しかった。北海道でワインの生産について研究している友達もいたので、興味のある人は調べてみてください。
4. 森林生物科学科(自然が好きなら天国)
森林の保全や生態学、バイオマスエネルギーなど、森林に関することを幅広く扱う学科です。木材、セルロースなど細かい部分から森林にアプローチしたり、森林と人間の関係性を扱ったり(ほぼ社会学ですね)。ミクロからマクロまでかなり幅広く森林について学べる印象です。実験系とフィールド系に分かれていて、実験などで細かいことをやりたい人も演習林やフィールドに出て森林に向き合いたい人も、どちらも許容されると森林の友達が言ってました。
50~60人と、多すぎず少なすぎない人数規模感で、ゆるく仲が良さそう。授業なども比較的選択に幅が利き、平和で自由なイメージです。森林には多くの友達がいますが、ひたすらに山や森林が好きな子や、バードウォッチングに傾倒している子、木材の成分を調べ続ける子など、それぞれの観点から森林・自然への愛を感じます。森林や林業系のサークルに入っている子も多く、そもそも山や自然、生態系に興味のある子が集まりがちなのでしょう。だからこそ芯の通った生き方を感じることが多く、良い刺激を受けています。入試の際には、応用生命や食品、資源などに比べてあまり人気が無いと聞きましたが、私から見るととても魅力的な学科だなぁと思います。
北海道や和歌山の演習林での実習の機会もあり、フィールドワークが好きな人にもオススメ。一応ですが、卒論も必須ではありません(ほとんどの人は当たり前に書きます)。比較的のんびりした雰囲気で、自由もききそうな学科です。
5. 資源生物科学科(自由度MAX!)
私が所属していた学科で、特徴はとにかく分野の幅が広いこと。動物、植物、微生物、昆虫、食品、水産など、「資源」となるものは何でも扱ってしまう巨大な学科です。定員も100人ほどと、農学部の中では圧倒的に多いです。
幅広い分野を学べるため、「まだやりたいことがはっきり決まっていない」「色々な分野を知ってから専門を決めたい」という、過去の私のような人には向いていると思います。授業の選択肢が豊富で、興味のある分野を自由に学べるのが魅力。
さらに、フィールドワークや実習系の授業が多いのも特徴です。2年生では毎週木津にある農場へ行って農作業を体験したり、長期休暇中には牧場でウシの生産を学んだり(水産実習ではシュノーケリングや微生物のサンプリングをすることも!)。他学科でも実習の機会はありますが、資源生物科学科は特に充実していて単位として認められる授業も多いので、ちょっと得した気分になります。
私自身も「座学だけじゃなく、フィールドワークに出たい」と思ってこの学科を選びました。当時は予備校の先生に「応用生命や食品は第一希望で出さないと通らないよ」と言われたりもして、悩みに悩んでの決断でしたが、結果的に、興味のある授業を自由に取ることができ、自分にはこの学科が合っていたと思います。他学科の授業も単位として認められる制度があったので、学科の枠を超えて興味のある分野に挑戦できたのも良かったです。
ただし、数年前からカリキュラムが変更され、1,2年生?の段階でコース(植物系、動物系、水産系など)を選ぶ必要が出てきました。私の頃よりは少し早い段階で専門を絞らなければいけませんが、それでも入学後にじっくり考えられるのはメリットだと思います。
もう一つ注意点として、学科の人数が多いため、自由に授業を選びすぎると「一緒に行動する友達がいない」という現象が起こる可能性があります。これは私の場合ですが、あまりにも自分の興味に任せて好きな授業ばかり取っていたので、友達と一切授業が被らず、誰とも話さず帰る日がよくありました(笑)。コース制の導入により、ある程度解消されているとは思いますが、自由度が高いぶん、自分で居場所やコミュニティを作る努力も必要かもしれません。
応生や食品に比べるとゆるめの印象ですが、3年生になると学生実験があります。(一応、必修ではありません。が、ほとんどの人が履修します)。そして卒論も必須ではないという珍しい学科です(ただし、これもほとんどの人は書きます)。この自由度の高さは賛否が分かれるところですが、入学後に「入ってみたけど思っていたのと違った」「他に熱中できるものが見つかった」というときに、ある程度の選択肢が残されているのはメリットでもあると私自身は思っています。(ただし、制度は年々変わるので、詳しくは最新の情報を確認してくださいね。)
この学科は、広く学びたい人、生物が好きな人、フィールドワークが好きな人、農学の中でも何をするか決まっていない人、自由に自分の学びをカスタマイズしたい人にはおすすめ。ただし、学科のまとまりがあまりないので、受け身の姿勢だと少し寂しくなることもあるかもしれません。
あと、これは京大生全般に言えることかもしれませんが、なかなか面白い人が多いです。分野の幅が広いからか、自由度が高いからか、結構ぶっ飛んで面白いことをしている友達が多い気がします。詳しくは割愛します。入ってからのお楽しみということで…(笑)。
自分が入っていた学科なので長くなってしまいました。ラスト、次に行きましょう。
6. 食品生物科学科(応用生命と並ぶ人気学科)
こちらも応用生命と並んで人気の学科。その名の通り、食品に関することを幅広く学ぶことができる学科です。食品の機能や発酵、微生物、バイオ燃料、栄養化学、酵素、医薬品、味覚など、かなり包括的に食品を扱うことができるのが特徴。実験を中心とした比較的ミクロな視点での研究を多く行っていて、食品会社や化粧品会社への就職が多いイメージです。食品やバイオに興味があるなら、満足度の高い学科だと思います。
印象としては、比較的女子が多く、品があって可愛い感じ(主観と偏見です)。全部で30人ほどとかなり規模が小さく、授業もほぼ必修のため、普段は基本的に学科のメンバーで行動することになります。おそらく教授たちとの距離も近く、しっかりと面倒を見てもらえるはず。放任主義の資源生物科学科とはえらい違いですね。
特に3年生は実験漬けでかなり多忙になりますが(食品の友達にスケジュールを見せてもらったら、ほぼフルコマで詰めっ詰めで仰天しました。。。)、実験でチーズを作ったり、ワインを作ったり(?)、私的には結構楽しそうに見えました。酒造に足を運んで発酵や醸造を学ぶ実習などもあったはず。私も醸造系の授業や品質管理、食品安全学の授業を取ったことがありますが、日々の食事や生活に結びつくことが多く興味深かったです。
応用生命と並び、この学科に入りたければ、おそらく第一希望で書かないと厳しいです。希望する人は、堂々と志望欄の一番上に書きましょう。応援しています。
まとめ:どの学科が向いてる?
以上、独断と偏見と主観による京都大学農学部の学科比較でした。(これは果たして役に立つのだろうか…)
大学で4年間過ごしてみて改めて思いますが、学科選びは、「何を学びたいか」だけではなく、「どういう大学生活を送りたいか」もかなり大事だと思います。
もちろん学科選びに正解なんてありません。興味があると思って入っても意外と全然ハマれなかったり、興味の無かった学科に入ったら意外と面白くてハマっちゃったり、こればかりは入ってみないとわかりません(笑)。
どれだけ自由な学科でも居場所が無いと面白くないかもしれないし、どれだけ忙しい学科に入っても、自分の時間を作り出している人はいます。最悪、入ってから転学科を考えることも、制度としては可能です。
一番大切なのは、自分自身が納得すること。どんな選択をしても、「あの時の自分にとってはベストな選択だったから仕方ないな」と思えることが大事なんじゃないかな、と思います。
受験期って、ついつい偏差値や周りの声を気にしてしまいがちですが、どうか自分の本当の気持ちに素直に(これが一番難しかったりするのですが…)、自分がスッと頷けるような道を進んでくださいね。
納得のいく選択に向けて、この記事が少しでも参考になったら嬉しいです。
もし可能なら、オープンキャンパスや学祭(11月)、塾や学校のOB・OGなど実際の学生に話を聞いてみたりするのもオススメです。限られた情報の中でも、できるだけ生の声を集めてみてください。
受験や学科選び全般について、質問フォームを作りました。回答方法もいくつか用意しています。院も合わせて6年間京大に通っていた身として答えられる部分は答えますので、モヤモヤを抱えている方は、よければご活用ください!
↓質問フォーム
※回答には時間がかかることがあります。ご了承ください。
※現在、ブログ用のSNSは作っていませんが、必要に応じて導入予定です。作成し次第ブログ記事でお知らせします。
受験生のみなさん、学科選びを後悔しないようにじっくり考えてくださいね!応援しています!
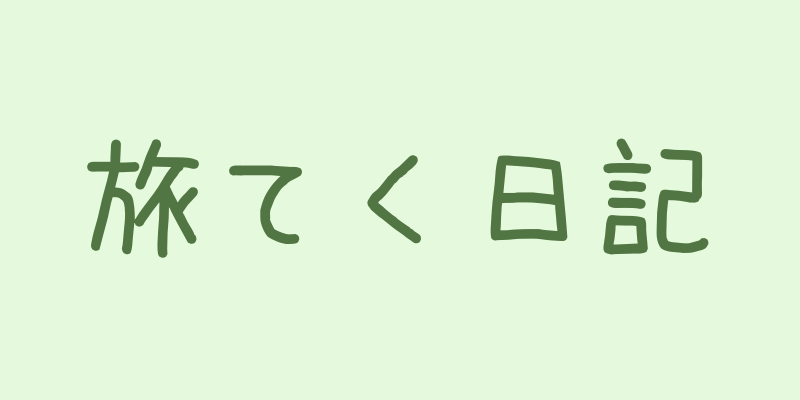



コメント